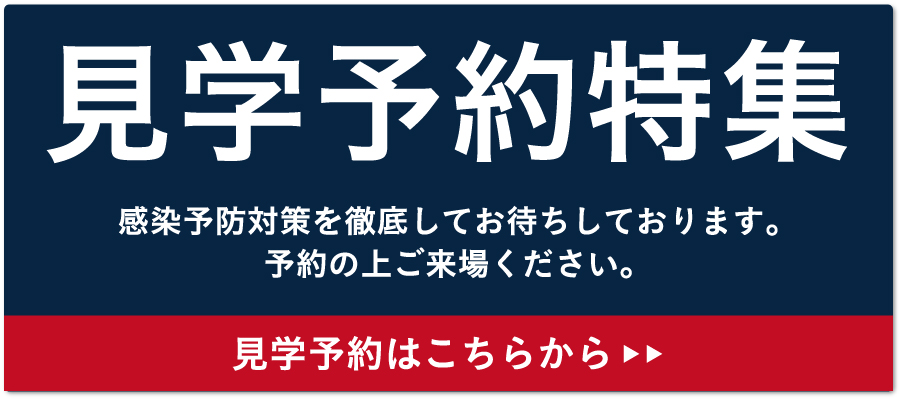住民税はいつから払う?
計算方法や新築の住宅ローン控除についても解説
住民税は一定の所得がある人が納める税金ですが、いつから払うのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
とくに、家の購入を考えるときは、いつから徴収されるのか、住宅ローン控除の条件はどうなるのかなど、気になる方も多いでしょう。
そこで本記事では、住民税を払うタイミングや、税額の計算方法などについて詳しく解説します。住宅ローン控除の説明もしますので、ぜひ参考にしてください。
住民税とは?

住民税とは、居住している自治体に納める地方税です。都道府県と市区町村で前年の1月から12月までに得た所得に対してそれぞれ徴収されます。たとえば、東京都新宿区に居住している場合は、都民税と区民税が併せて課税・徴収されます。
税率は以下のとおりです。
道府県民税(都民税):4%
このように、住民税の税率は合計で10%になります。
なお、住民税の主な用途は、教育や福祉、清掃事業などの地域公共サービスです。
所得割と均等割が課税される
住民税は、所得の額に応じて課税される「所得割」と、所得金額を問わず個人が等しく負担する「均等割」の合計額になります。
所得割とは、所得金額に比例して課税される税額です。課税額は前年の所得から算出されます。計算方法は「所得金額-所得控除金額」です。
所得控除の種類は所得税とほぼ同じですが、住民税は控除額が少なくなります。
均等割
均等割は、市町村民税(特別区民税)3,500円と道府県民税(都民税)1,500円の合計額です。この金額は、平成26年度から平成35年度まで全国一律となります。
均等割は所得を問わず負担する税金ですが、以下のような人は課税の対象外となります。
・所得金額が一定の金額以下の人
・生活保護を受けている人
など
住民税はいつから払う?
住民税の徴収方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があります。それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。
普通徴収の場合
普通徴収は、個人事業主などが対象となる徴収方法です。給与所得者以外は普通徴収になると考えていいでしょう。
毎年6月ごろには、確定申告書などをもとに算出された納税通知書が届きます。納税通知書には住民税額や納期などが記載されているので、誤りがなければ期日までに納付しましょう。納付方法は一括と4回分割の2種類から選択可能です。
特別徴収の場合
特別徴収は、給与取得者や65歳以上の公的年金受給者が対象の徴収方法です。企業や日本年金機構などが特別徴収義務者となって、納税者から税金を徴収・納付します。
住民税額は自治体から企業に通知されるので、各企業は6月から翌年5月までの間、給与から住民税を天引きして市区町村に納付します。
なお、給与所得以外にも課税対象となる所得がある場合は、「所属している企業に合算して特別徴収してもらう」または「普通徴収で納めるか」のいずれかを選択することが可能です。確定申告書に選択欄があるので、自分が希望するほうを選択して提出しましょう。
新入社員の住民税は2年目から
住民税は前年の所得に対して課税されます。そのため、前年に所得がない新入社員は住民税が課税されません。
なお、4月入社の場合、社会人2年目の住民税は4~12月の所得をもとに計算されます。また、社会人3年目は前年の1~12月分の所得に課税されます。そのため、社会人2年目よりも3年目のほうが税額は上がります。
退職した場合も前年課税される
住民税は前年度の所得に対して発生するため、退職後も前年度分の住民税を納める必要があります。
長年にわたって特別徴収の天引きが続いていると、住民税を納めているという意識が薄くなりがちなので注意しましょう。
退職後に所得が少なくなった場合、前年の住民税が納付できなくなることもあります。退職する際には、当年度分の住民税は翌年に納付することを忘れないようにしましょう。
なお、退職後に別の会社へ就職する場合は、転職先の企業で特別徴収を継続してもらえます。ただし手続きには時間がかかることもあるため、以下のような対策をするとこも可能です。
・1度普通徴収に切替える
・退職時に数か月分の住民税を天引きしてもらう
住民税はいくら?計算方法について
納付する住民税額は、納税通知書に記載してあります。しかし、天引きされている住民税を気にしない方も多いようです。改めて、住民税の計算方法を確認しておきましょう。
1.課税所得金額の算出
まずは課税所得金額を算出します。算出方法は以下のとおりです。
給与所得控除は、給与等の収入金額によって下表のように変わります。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
| 162万5千円以下 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
2.所得割額を計算する
算出方法は以下のとおりです。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得割に該当します。確定申告書であれば、申告書Aの所得金額の合計です。所得控除には医療費控除や配偶者控除などがありますが、適用条件は人によって異なります。
ただし、基礎控除はすべての納税義務者に適用されます。控除額は、所得の額によって下表のように変わります。
| 所得額 | 基礎控除額 |
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円(適用なし) |
3.税額控除を差し引く
「2」で算出された所得割額から税額控除を差し引きます。税額控除については後述します。
4.均等割を加算する
「3」で算出された所得割額から税額控除を差し引いた額に均等割を加算し、以下のように合算して住民税額を算出します。
・市町村民税(特別区民税)年額=市町村民税(特別区民税)所得割額+市町村民税(特別区民税)均等割額
・道府県民税(都民税)年額=道府県民税(都民税)所得割額+市町村民税(特別区民税)所得割額
・住民税年額=市町村民税(特別区民税)年額+道府県民税(都民税)年額
実際の計算例を見てみましょう。
条件:給与所得額400万円、所得控除40万円、税額控除なし
400万円×20%+44万円=課税所得124万円
124万円-(所得控除40万円+基礎控除43万円)=所得割41万円
市町村民税(特別区民税):(41万円×6%)+均等割3,500円=28,100円
道府県民税(都民税):(41万円×4%)+均等割1,500円=17,900円
住民税年額合計:28,100円+17,900円=46,000円
住民税は控除が多いほど節税になる
住民税には、以下のような控除があります。
・所得控除
所得控除とは、所得額より差し引ける控除です。税率をかける前の課税所得から差し引きます。
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
・税額控除
税額控除は、算出された所得税額から直接控除します。
・配当控除
・外国税額控除
・政党等寄付金特別控除
・認定NPO法人等寄付金特別控除
・公益社団法人等寄付金特別控除
・住宅借入金等特別控除
・住宅耐震改修特別控除
・住宅特定改修特別税額控除
・認定住宅新築等特別税額控除
いつまで新築住宅ローンで住民税が減額される?
2021年で終了予定だった住宅ローン控除ですが、2022年の税制改正によって2025年まで延長されることになりました。そのため、新築住宅は2025年12月末までに入居すれば、住民税の控除が適用されます。
ただし、2023年末以降に入居すると、借入限度額と控除の上限額が低くなるので注意が必要です。
・2023年末までに入居した場合
| 住宅の種類 | 借入限度額 | 最大控除額 |
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 | 455万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 409.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 364万円 |
・2024年〜2025年末までに入居した場合
| 住宅の種類 | 借入限度額 | 最大控除額 |
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 409.5万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 318.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 273万円 |
所得税から控除しきれなかった場合は住民税から控除されますが、改正前と改正後では、控除の上限が以下のように変わります。
・改正前:前年度課税所得×7%、最大136,500円
・改正後:前年度課税所得×5%、最大97,500円
まとめ

住民税は課税対象になった翌年から納めます。会社員のような給与所得者は天引きされるので、自分で計算・納付する必要はありません。
給与所得者以外の納付方法は自治体によって異なりますが、年4回に分けて納付するのが一般的です。毎年6月ごろには、確定申告書などをもとに算出された納税通知書が届くので、納付書の指示に従って納めるようにしましょう。
住宅ローン控除は2025年まで延長されることになったため、新築住宅の購入者で上限に該当した場合は、住民税も控除されます。ただし、最大控除額は住宅の種類や入居した時期によって変わります。
賢く減税するためにも、新しい制度や適用条件を確認しておきましょう。