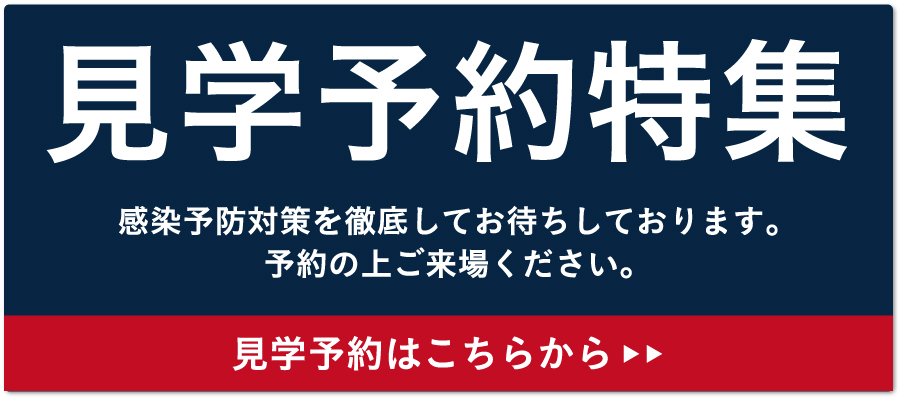固定資産税評価額とは?
税金の計算方法や調べ方までその仕組みを解説
住宅を購入した方が、その後納付していくことになる固定資産税。
この固定資産税は、どのような計算方法により算出されているのか、その仕組みはご存じでしょうか。
固定資産税を算出するために使われるのが、「固定資産税評価額」と呼ばれる住宅価格の指標のひとつです。
今回はこの固定資産税評価額について、実際の計算方法や固定資産税評価額の調べ方などとともに徹底解説していきます。
1. 固定資産税評価額とは?

固定資産税評価額は、冒頭でもご紹介したように固定資産税を算出する際に使われる不動産の評価額のひとつです。
土地には決まった1つの価格というものはなく、使用する目的に応じて様々な価格が用いられます。
例えば土地の売買の際に基準とされる地価公示価格や、相続税・贈与税の計算に使われる路線価などですね。
固定資産税評価額もそのひとつで、固定資産税をはじめ以下のような税金の算出に用いられます。
| 固定資産税 | 不動産の所有者に課税される税金 |
| 都市計画税 | 都市計画法で定められた市街化区域内に不動産を所有している場合に課税される税金 |
| 登録免許税 | 登記申請にかかる税金 |
| 不動産取得税 | 不動産の取得時にかかる税金 |
固定資産税評価額は、固定資産評価基準として定められた明確な基準をもとに、都や各市町村などの自治体で決められるものです。
面積や場所、立地、建物の構造や大きさ、築年数など様々な要素によって決定されています。
1-1. 課税標準額との違い
固定資産税評価額と混同されやすいのが、「課税標準額」です。
「課税標準額」とは、実際に税額を決定する際に最終的に使用する不動産額すべてを呼ぶもので、固定資産税に関するものは「固定資産税課税標準額」とも言われます。
固定資産税評価額は確かに固定資産税の決定の基準として用いられますが、実際の計算には各特例や控除などを考慮した課税標準額が使われるため、固定資産税評価額と課税標準額に差があるという場合も多々あるでしょう。
2. 固定資産税評価額の調べ方
自身の所有する不動産などの固定資産税評価額を知るためには、次のような方法があります。
2-1. 課税明細書を確認する
まず、一番簡単にできるのが課税明細書を確認することです。
毎年自治体から送られてくる固定資産税納税通知書とともに送られてくるもので、課税対象になっている不動産の情報が記載されています。
その中の、「価格(もしくは評価額)」という欄を見ると、固定資産税評価額が記載されています。
2-2. 固定資産課税台帳を閲覧させてもらう
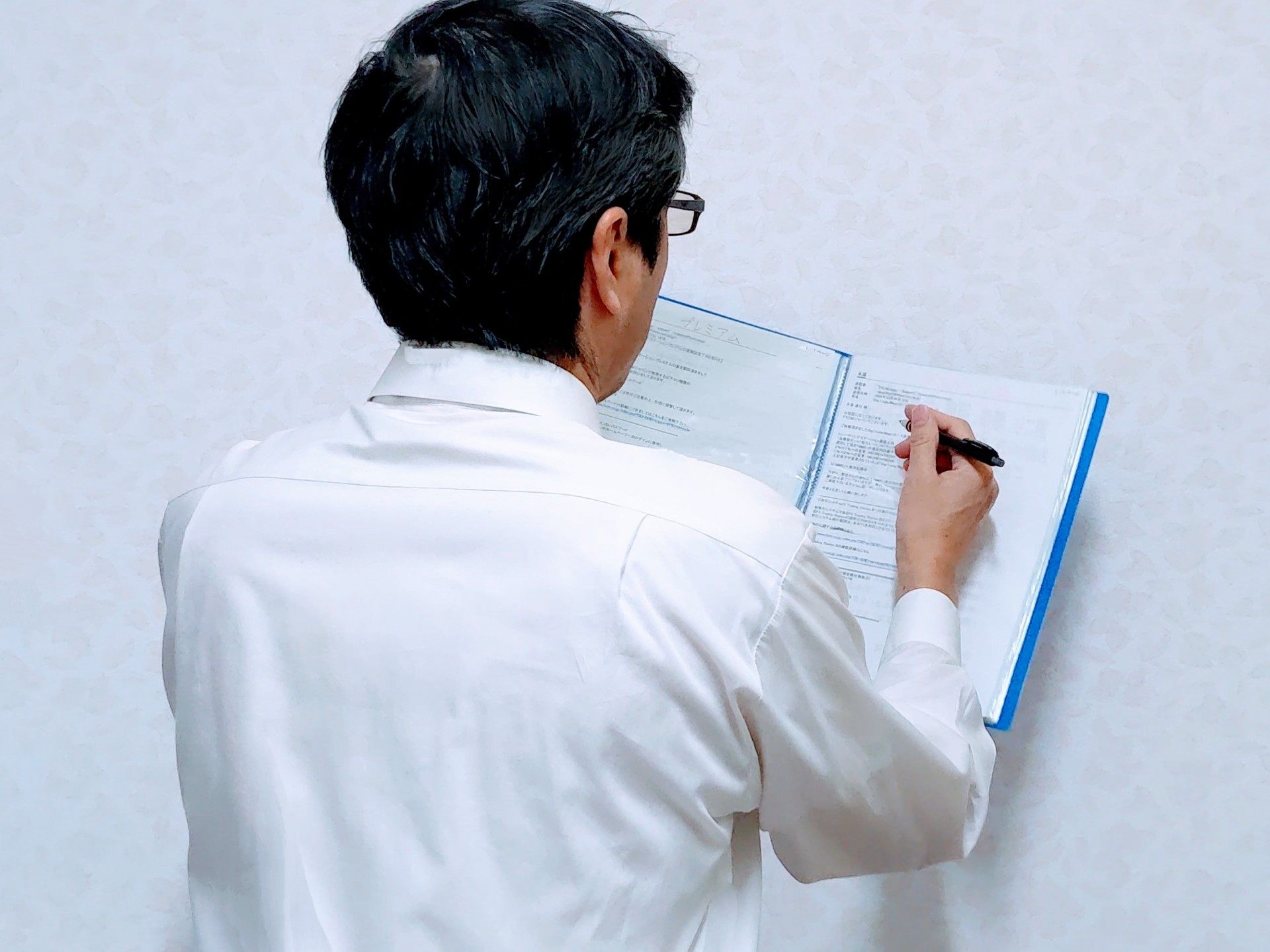
各自治体には、固定資産課税台帳と呼ばれる固定資産となる不動産の所在地や所有者、固定資産税評価額などの情報が記載された帳簿が存在します。
所有する不動産の所在地の役所に申請すれば閲覧することができるので、課税明細書が手元にないけれど確認したいという方は問い合わせてみましょう。
2-3. 固定資産評価証明書を発行する
前述の固定資産課税台帳に掲載されている情報を証明するための固定資産評価証明書も、役所に申請すれば手に入れることができます。
固定資産税評価額が見られることはもちろんですが、不動産取引や贈与など登記を行う場合には必要な書類ですので覚えておきましょう。
申請には申請書や本人確認書類の用意、また手数料が必要となるので注意してください。
3. 固定資産税の計算方法
課税明細書などで固定資産税評価額が分かったら、大まかに固定資産税を計算することも可能になります。
固定資産税は、次のような式で計算されています。
例えば固定資産税評価額が1,500万円で、特例や控除などがなく課税標準額とイコールの場合には、1,500万円×1.4%で21万円が固定資産税額となりますね。
多くの標準税率とされる1.4%ですが、中には標準税率の異なる地域もあるため、事前に自治体の税率を確認しましょう。
3-1. 固定資産税評価額から算出できるその他の税金
固定資産税評価額は1章でもご紹介したように、他にも
● 都市計画税
● 登録免許税
● 不動産取得税
といった税金の算出にも使用できます。
それぞれ、以下のような計算方法で出すことができます。
| 都市計画税 | 固定資産税評価額(課税標準額)× 0.3% |
| 都市計画税 | 都市計画法で定められた市街化区域内に不動産を所有している場合に課税される税金 |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額(課税標準額)× 3%(住宅用地の場合) |
| 不動産取得税 | 登記内容によって税率が異なる |
3-2. 固定資産税はいつから下がる?
固定資産税額は、建物の築年数によって低下することはご存じでしょうか。
時間とともに建物は経年劣化していくため、その価値の低下が固定資産税評価額にも影響し、固定資産税の低下にもつながります。
鉄骨や木造など、建物の構造や素材ごとに明確に固定資産税評価額の劣化補正基準が決められており、この劣化の補正割合を「経年減点補正率」と呼びます。
評価は新築からでも1年が経つごとに徐々に下がっていき、はじめの1年ですでに新築時の評価の80%ほどに低下します。
しかし、固定資産税評価額が見直されるのは3年ごとになるため、実際に固定資産税の減額に表れるのは3年後になりますね。
4. 固定資産税を抑えるには?

固定資産税評価額によって決められる固定資産税ですが、出費を抑えるためにも、できる限り減らすことができればと思っている方も多いのではないでしょうか。
条件によっては、固定資産税を抑えることは可能です。
4-1. 特例を利用する
固定資産税には、条件を満たしていると利用できる特例や減額措置があります。
代表的なのが、次の3つの特例です。
▼住宅用地の特例
所有しているのが住宅用の家屋である場合、住宅用地の特例が使用でき、以下のような軽減措置が受けられます。
| 小規模住宅用地(200㎡以下) | 課税評価額×1/6=実際の課税評価額となる |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 課税評価額×1/3=実際の課税評価額となる |
▼新築住宅の特例
新築住宅では、3年間(3階建て以上で耐火基準を満たしているものは5年)、固定資産税額が1/2になる特例を受けることができます。
こちらは令和6年3月31日までに建てられたものが対象とされていましたが、対象を令和8年3月31日までに延長することが発表されたため、今後もしばらく利用できます。
▼リフォーム特例
築10年以上の住宅においては、条件を満たしたバリアフリーリフォームや省エネリフォームを行った場合、次年度の固定資産税額から1/3が減額されます。
4-2. 固定資産税は建物や設備でも異なる
固定資産税評価額は、単に土地の大きさや住宅の大きさで決められるわけではありません。
基本的には建築にかかった価格が参考にされるため、例えば木造よりも建築費用の掛かりやすい鉄筋の方が高くなるなど、構造や設備の室などにも左右されます。
構造によって評価が変わるため、建物が実際の構造通りの評価を受けているかどうかも確認しましょう。
まとめ
今回の記事では、固定資産税の算出に用いられる不動産評価額、固定資産税評価額について、その概要や計算方法、また固定資産税の抑え方まで詳しくご紹介しました。
固定資産税評価額は土地の価値だけでなく建物の構造や立地などあらゆる要素で決定されるため、評価額自体を自身で算出するのは難しいでしょう。
気になる方は、課税明細書や固定資産評価証明書を確認してみると良いですね。
また、固定資産税にはご紹介したように特例なども多くあります。
少しでも税金を抑えるために、条件に合う方はぜひ活用してみてください。