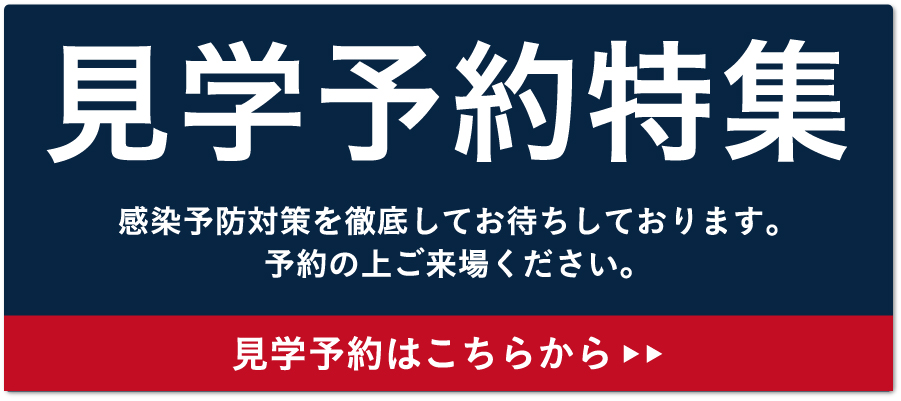坪数によって変わる固定資産税!
計算方法も紹介
「固定資産税」は物件探しやマイホーム購入時によく耳にする言葉です。
実は、固定資産税は家屋調査によって課税標準額が決められることをご存知でしょうか?
家屋調査の流れは、まずマイホーム購入後に役所から連絡があり調査日を打ち合わせます。
その後に調査員が自宅に訪れ、屋内や屋外の調査を行います。
その際に、平面図や立面図などの書類があるとスムーズに調査が進むでしょう。
家屋調査は、30分〜1時間ほどで完了することが一般的です。
固定資産税には、税額が高くなるラインがあります。
今回は、固定資産税が何坪から高くなるのかについて詳しく解説します。
固定資産税について

固定資産税とは、土地、家屋、償却資産などの固定資産を所有する人が、その資産価値に応じて納める税金のことです。
固定資産税は地方税に分類され、納付先は各自治体となります。徴収された固定資産税は、
わたし達が日々利用する公共施設や道路整備、介護・福祉などの行政サービスに使われます。
固定資産税の税額は、以下の3つの要素によって決まります。
・課税標準額
・税率
・軽減措置
課税標準額とは、固定資産の評価額のことです。
土地は公示地価または路線価、家屋は固定資産評価基準、償却資産は取得価額や使用状況によって評価されます。
また、課税標準額は実勢価格のおよそ7割といわれているため、地価の高いエリアの土地ほど高くなる傾向にあります。
課税標準額の調べ方は以下の3つです。
・自宅に送られてくる固定資産税評価明細書を確認する
・役所で固定資産評価証明書を入手する
・役所で固定資産課税台帳を閲覧する
固定資産税の税率は、都道府県や市区町村によって異なり、一般的に土地の税率は家屋の税率よりも高く設定されています。
また、軽減措置とは、固定資産税の税額を減額または免除する制度のことです。
例えば、住宅用地や災害被災者に対しては、固定資産税の税額を減額または免除する措置があるため、有効利用すると良いでしょう。
土地面積60坪を超えたら固定資産税が高くなる
土地にかかる固定資産税は60.5坪を超えると高くなります。
固定資産税には軽減措置があり、200平米(60.5坪)以下の敷地は固定資産税が軽減されるのです。
具体的な適用条件は以下のとおりです。
②200㎡以上の一般住宅用地は、軽減率が評価額×1/3
このように、②の場合は減額幅が小さくなるため、200平米(60.5坪)を超えると固定資産税が高くなります。
敷地面積190平米で評価額2,400万円の土地の場合は敷地すべてに①が適用されます。
という計算となり、軽減後の評価額は400万円です。
敷地面積400平米で評価額3,600万円の土地の場合、200平米ずつ①と②が適用されます。
②「1,800万円(3,600万円の1/2)✕1/3=600万円」
これにより「①300万円+②600万円=900万円」で軽減後の評価額は900万円です。
新築住宅は床延面積84.7坪を超えたら固定資産税が高くなる
新築住宅にも固定資産税の軽減措置が用意されており、延床面積が84.7坪以上で固定資産税が高くなります。
新築住宅に対する固定資産税の減額の要件は以下のとおりです。
・居住部分の割合が1/2以上
・延床面積が50平米(15.1坪)以上280平米以下(84.7坪)以下
このことから、新築住宅の延床面積が84.7坪を超えると固定資産税が高くなります。
また、軽減措置の内容は、新築住宅は3年間、新築マンションは5年間、認定長期優良住宅は新築住宅が5年間、
新築マンションは7年間、建物にかかる固定資産税が1/2に減額されるというものです。
【固定資産税の軽減措置】
| 住宅用地 | 敷地面積が200平米(60.5坪)以下(小規模住宅用地) | 評価額×1/6 |
| 敷地面積が200平米(60.5)以上(一般住宅用地) | 評価額×1/3 | |
| 新築住宅 | 延床面積が50平米(15.1坪)以上280平米以下(84.7坪)以下 | 固定資産税が1/2 ※新築住宅は3年間 新築マンションは5年間 認定長期優良住宅は5or7年間 |
固定資産税はいくら?計算方法
固定資産税は、所有する固定資産の評価額(課税標準額)に、標準税率となる1.4%を掛けて算出します。
※ただし、自治体によって1.5%や1.6%など異なることがあるため、気になる方は確認するようにしましょう。
固定資産税の計算式は以下のとおりです。
固定資産税=評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)
シミュレーション 1
前提条件は以下のとおりです。
・土地の評価額:4,200万円(敷地面積150平米)
・建物の評価額:2,500万円(延床面積100平米)
・築年数:2023年5月(新築)
・税率:1.4%(都市計画税は考慮せず)
①土地の固定資産税額
課税標準額
=土地の評価額×1/6
=4,200万円×1/6
= 700万円
固定資産税額
=課税標準額×税率
=700万円×1.4%
=9.8万円
②家屋の固定資産税額
課税標準額=2,500万円
固定資産税額
=課税標準額×税率× 1/2 (新築住宅の減額措置)
=2,500万円×1.4%×1/2
=17.5万円
シミュレーション 2
前提条件は以下のとおりです。
・土地の評価額:3,600万円(敷地面積400平米)
・建物の評価額:2,000万円(延床面積120平米)
・築年数:2023年7月(新築)
・税率:1.4%(都市計画税は考慮せず)
①土地の固定資産税額
・課税標準額(小規模住宅用地)
=土地の評価額×1/6
=3,600万円×1/2×1/6
= 300万円
・課税標準額(一般宅用地)
=土地の評価額×1/3
=3,600万円×1/2×1/3
= 600万円
固定資産税額
=課税標準額×税率
=300万円+600万円×1.4%
=12.6万円
②家屋の固定資産税額
課税標準額=2,000万円
固定資産税額
=課税標準額×税率× 1/2 (新築住宅の減額措置)
=2,000万円×1.4%×1/2
=14万円
固定資産税の納付の仕組み

固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産を所有している人が納める税金です。
原則として、年4回の納期ごとに分割して納付する仕組みとなっています。
また、納税通知書が郵送される時期は各自治体によって変わり、毎年4〜6月頃に自宅に郵送されます。
納期限は原則として7月、9月、11月、1月の各月末です。
ちなみに、東京都23区内の場合は、毎年6月1日(土日の場合は翌開庁日)に納税通知書が送付されます。
支払い方法は、金融機関やコンビニでの現金支払いや口座振込み、クレジットカード払いやスマホ決済に対応している自治体もあります。
ただし、支払い方法は各自治体によって異なるため、事前にホームページ等で確認しましょう。
また、クレジットカード払いの際は手数料がかかったり、納税証明書の発行に手間がかかったりする注意点があります。
また固定資産税の納付忘れがあると、延滞金が発生します。
延滞金の年率は各自治体によって異なりますが、期限から1ヶ月を過ぎると割合が高くなります。
そして納税督促を受けた場合は、財産の差し押さえなどの強制執行が行われる可能性があることも知っておきましょう。
固定資産税は戸建て住宅だけでなく、マンションにも支払義務が発生します。
したがって、マンションを賃貸契約ではなく「購入」した場合には、次の納期に固定資産税を納付する必要があるため注意が必要です。
さらに、戸建て住宅だけでなく、マンションの固定資産税も「土地」と「家屋」の両方に課税されます。
家屋部分は経年劣化が考慮され、税額は年々下がっていくケースが一般的なため、新築時が最も評価が高くなる仕組みとなっているのです。
固定資産税がかからない家は?
固定資産税には、免税点という所有していても課税されないケースがあります。
不動産の免税点は、土地にかかる課税標準額の総額が30万円、家屋にかかる課税標準額の総額が20万円に満たない場合です。
注意点は、免税点は「納付額」ではなく「課税標準額」ですので間違えないようにしましょう。
固定資産税を節約する方法
固定資産税は、不動産の所有者がかならず支払わなければいけない税金ですので、できるだけ節約したいものです。
固定資産税を節約する方法としては、以下があげられます。
・新築住宅を購入する
・長期優良住宅の認定を受ける
先述した通り、新築住宅を購入することで、3年間固定資産税の減税措置を受けることができます。
さらに、長期優良住宅の認定を受ければ、減税措置が5年に延長されます。
少しでも固定資産税を節約して新築住宅を購入したいのであれば、長期優良住宅のことを詳しく理解しておきましょう。
>> Vol.106 「長期優良住宅は得になる?定義や5つの嬉しいメリットについて解説」
まとめ
この記事では、固定資産税が坪数によって変わる仕組みの説明や固定資産税のシミュレーションを行いました。
固定資産税は、敷地面積が60.5坪を超えると高くなり、新築住宅の場合は延床面積が84.7坪を超えると高くなります。
マイホーム探しの際は、敷地面積・延床面積の希望や譲れない条件をよく考え、固定資産税を含めた費用を想定する必要があります。
固定資産税など、住宅にかかる費用についてさらに詳しく知りたい方はポラスの分譲住宅までお気軽にご相談ください。
>> ポラスの来店予約はこちらから